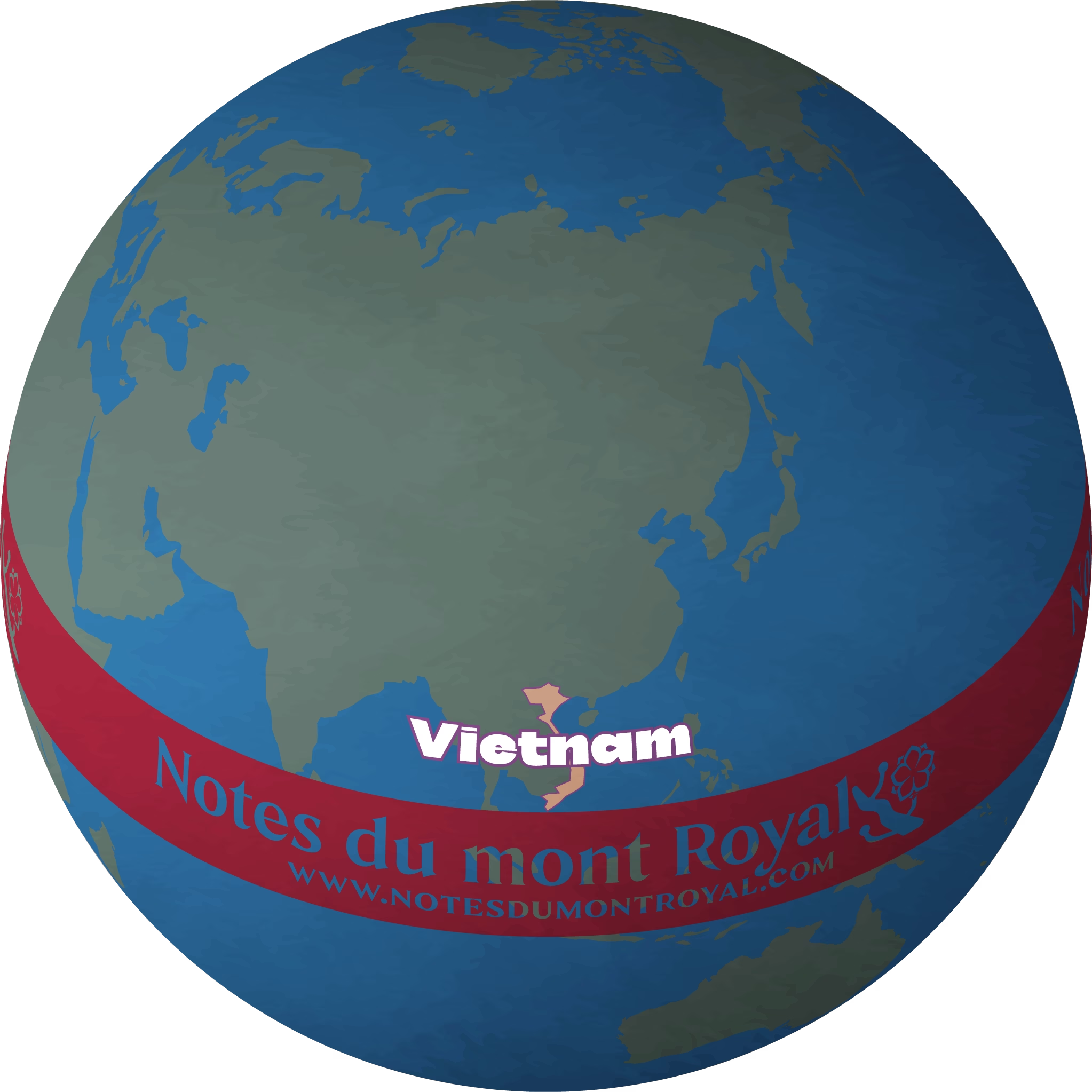自らを探求した者――ヘラクレイトスの偉大さと孤独
フランス語からの翻訳
ヘラクレイトスは、紀元前五世紀、エフェソスからアルテミス神殿に奉納された巻物の断片を通じて、悠久の時を超えて我々のもとに届く。その巻物が連続した論文であったのか、あるいは引用の偶然によって我々に伝えられたような孤立した思想の集まりであったのかは、今なお議論の的である。いずれにせよ、ヘラクレイトスはそこで、驚きを誘うような、簡潔で巫女的な文体を用い、預言者の口調と哲学者の言葉遣いを同時に帯びていた。そこから、「暗き者」あるいは「晦渋なる者」(Σκοτεινός)という、その名にしばしば冠せられる形容が生まれたのだが、それでも私にはいささか誇張に思われる。「なるほど、〔その〕書物は取りつきにくく、読みにくい。夜は暗く、闇は深い。しかし、一人の秘儀参入者が汝を導くならば、真昼の太陽よりもなお明るく、その書の中を見通すであろう」(『ギリシア詞華集』、パラティヌス写本に基づく)。その教説から我々に残された輝きは、神秘的に退いた嵐の閃光のようであり、他に類なき火をもって前ソクラテス期の夜を引き裂いている。ヘーゲルは「思考の光」の迸りを辿りつつ、ヘラクレイトスのうちにこの上なく光り輝く中心的人物を認めた。ハイデガーはさらに踏み込む。「ヘラクレイトスは〈暗き者〉と呼ばれている。しかし彼こそ〈明るき者〉である。なぜなら彼は、照らし出すものを語り、その光を思考の言葉のうちに招き入れようと試みているからである」1ハイデガー、マルティン『論文と講演』(Essais et Conférences)、アンドレ・プレオーによるドイツ語からの仏訳、ジャン・ボーフレ序文、パリ:Gallimard、「試論」叢書、1958年。。
拒絶の王権
この見かけの晦渋さに加え、ヘラクレイトスには同胞に対する根深い矜持と軽蔑の念があった。哲学者が誇り高きとき、それは決して中途半端なものではない。王位継承者でありながら、彼は何の未練もなく兄弟に王の尊厳を譲り、さらには「悪しき国制に支配されている」(πονηρᾷ πολιτείᾳ)と断じた国のために立法することを拒んだ。こうして彼はアルテミス神殿の聖域に退き、子どもたちと距骨遊びに興じた。物見高い者たちが群がれば、彼はこう投げつけた。
「なぜ驚くのか、愚か者どもよ。こうしているほうが、お前たちとともに国政に携わるよりましではないか。」(Τί, ὦ κάκιστοι, θαυμάζετε; Ἢ οὐ κρεῖττον τοῦτο ποιεῖν ἢ μεθ’ ὑμῶν πολιτεύεσθαι;)
ディオゲネス・ラエルティオス『哲学者列伝』第九巻、ジャック・ブリュンシュヴィクによるギリシア語からの仏訳、マリー=オディール・グレ=カゼ監修『哲学者列伝――生涯と学説』(Vies et Doctrines des philosophes illustres)所収、パリ:Librairie générale française、「ポショテック」叢書、1999年。
この賢者は誰も必要とせず、学者たちの交わりさえ蔑んだ。しかしながら、それは無感覚な人間ではなかった。人間の存在を織りなす不幸を嘆くとき、その目には涙が浮かんだ。「我は自らを探求せり」(Ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν)と彼は告白する。あたかも、デルポイの格言「汝自身を知れ」を真に実現した唯一の者であるかのように。ニーチェは、この自足の聖なる戦慄を感じ取るであろう。「アルテミス神殿のエフェソスの隠者が味わった孤独の感情がいかなるものであったか、もし自ら最も荒涼とした最も険しい山中で恐怖に打ちすくめられるのでなければ、何人も推し量ることはできない」と、力への意志の哲学者は語る2ニーチェ、フリードリヒ『ギリシア悲劇時代の哲学』(La Philosophie à l’époque tragique des Grecs)、ミシェル・アールおよびマルク・ド・ロネーによるドイツ語からの仏訳、マルク・ド・ロネー監修『著作集』(Œuvres)第一巻所収、パリ:Gallimard、「プレイヤード叢書」、2000年。。
万有流転の眩暈
ギリシア世界のもう一方の端で、エレア学派が存在を氷のような不動性に凍結していたのに対し、ヘラクレイトスは統一を絶えざる運動のうちにある河と構想する。その河は、常に異なりながらも同一であり続け、新たな波が絶え間なく古い波を押しやっていく3この比喩によって、ヘラクレイトスが語っているのは、単に存在が浮沈と衰退に運命づけられているということだけではなく、いかなる事物もこれやあれで ある のではないということ、すなわちそれに なる のだということである。世界はキュケオーン(κυκεών)に似ている。ぶどう酒、おろしたチーズ、大麦粉を混ぜたこの飲料は、その粘りのある一体性を攪拌によってのみ保っている。攪拌が止めば、構成要素は分離し、重いものは沈み、この祭祀的飲料はもはや存在しなくなる。かくして運動こそが対立物の結合の構成要素であることが明らかとなる。「キュケオーンもまた、かき混ぜなければ分離する」(Καὶ ὁ κυκεὼν διίσταται μὴ κινούμενος)。。持続するという通俗的な幻想に抗して、何ものも安定しない。「万物は流転する」(Πάντα ῥεῖ)、「すべては 生成 である」(ヘーゲル)、「あらゆる物は〔…〕絶えず揺れ動く〔…〕。私は存在を描くのではない。私は移行を描く」(モンテーニュ)。
万物の流転がもたらす帰結として、すべてはその反対物へと転化する。存在が変化のうちにのみ存在するならば、それは必然的に二つの対立する項の中間にある。あらゆる瞬間において、二つの相反する性質が接する、あの捉えがたい境界に立ち会っている。人間自身にも適用される恐るべき法則であり、各年齢は前の年齢の死である。
「嬰児は幼児のうちに消え去ったのではないか。幼児は少年のうちに、少年は青年のうちに、青年は若者のうちに、そして〔…〕壮年は老人のうちに〔…〕消え去ったのではないか。おそらく〔…〕自然は、最期の死を恐れるなと、我々に静かに教えているのではないか。」
アレクサンドリアのフィロン『ヨセフについて』(De Iosepho)、ジャン・ラポルトによるギリシア語からの仏訳、パリ:Éditions du Cerf、「フィロン著作集」叢書、1964年。
宇宙的遊戯の美学
生の悲劇的肯定を求めて、ニーチェはエフェソスの隠者を最も近しい先祖とする。「世界は、真理への永遠の欲求において、〔…〕永遠にヘラクレイトスを必要とする」と彼は宣言する。そしてまた別の箇所で、
「〔…〕ヘラクレイトスとの交わりは、他の何にも増して私を安心させ、慰めてくれる。無常と 滅亡 への同意、矛盾と戦いへの「然り」、存在という概念そのものの拒絶を含意する 生成――このうちに、私は〔…〕かつて構想された思想のうち、私の思想に最も近いものを認めなければならない。」
ニーチェ、フリードリヒ『反キリスト者』(L’Antéchrist)、『この人を見よ』(Ecce homo)所収、ジャン=クロード・エメリーによるドイツ語からの仏訳、パリ:Gallimard、「フォリオ」叢書、1974年。
このドイツの哲学者がそこに見出したもの、それは何よりも、ショーペンハウアー的悲観主義への解毒剤であった。いわゆる過失、不正、矛盾、苦悩の軛のもとにたわむどころか、現実はあらゆる道徳から解き放たれる。それは「遊ぶ子ども、駒を動かす子ども――子どもの王権」(παῖς […] παίζων, πεσσεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη)である。ヘラクレイトスがアルテミス神殿で騒がしい子どもたちの遊びに加わったのは、そこですでに「世界という大いなる子どもの遊び」、すなわち神を瞑想していたからである。力への意志はここにおいてニーチェの精神のうちにその輪郭を現す。建設し、破壊する芸術家的な力であり、あちこちに小石を置き、あるいは砂の山を積み上げてはまた崩す子どもの崇高な無垢のうちに、善悪の彼岸で発揮される力である。「暗き者」の歩みを追ってこそ、ニーチェは「反キリスト者、すなわち世界の道徳的意味を拒絶する者になろうとする」のである。